�|�ŋ߂��̐l���ĂȂ����nj��C�H�@�C�L�C�L�ƌ��C�ł�����Ă�������s����ɏЉ�邱�̃R�[�i�[�B��16��ڂɓo�ꂵ�Ă��������̂́A�����V���ҏW�ψ����_���ψ��i�������݁j�Ƃ��ăG�W�v�g�̃A���N�T���h���A�ɍݏZ�A�����̑�������������|�[�g����������ד�����i26�j�ł��B
�i��ށE��/�R�{ ��j

|
�y�v���t�B�[���z
- ���ד��i���킩�݁E�₷�̂�j
- 1956�N���܂�A54�^26��
- ����8�N�Ԃ�Δn�ʼn߂����A��3�Ŏ������ɓ]���A�k���ցB
- ���O���w�i������w�O����w���j�A���r�A��Ȃɐi�w�B�݊w���ɁA�G�W�v�g�E�J�C����w���w�B
- 1981�N�ɒ����V�����ЁB���m�A���l���x�ǁA�w�|�����o�ĊO�Ɉڂ蒆���Ŋ���B
- 1994�N����1998�N�܂Œ����A�t���J���Lj��Ƃ��ăJ�C�����݁B
- 2001�N�G���T�����x�ǒ��A2002�N�����A�t���J���ǒ����C�A2003�N�o�O�_�b�h�x�ǒ������B
- 2002�N�A�G���T�����x�ǒ�����ɍ��ەɍv�������W���[�i���X�g��\������w�{�[���E��c�L�O���ۋL�ҏ܁x����܁B
�A���t�@�g�������{�c���Ƃ̒P�Ɖ�Řa���ւ̓W�]��������Ȃǂ̃p���X�`�i���ւ̐��͓I�Ȏ��g�݂ƁA"�����"�Ƃ����W���[�i���X�g�̌��_���т����p�����A�����]�����ꂽ�B
- �C���N�푈�ł̓o�O�_�b�h�ח����2003�N4���Ƀo�O�_�b�h���肵�A2004�N9���܂ł�1�N���̂����A�̂�300���ȏ�o�O�_�b�h�ɗ��܂����B
�����̋L�^�͒����w�C���N��N�`�����V�����h���̕`�x�i�����V���Њ��j�ɂ܂Ƃ߂��Ă���B
- 2006�N�ɋA���B�ҏW�ψ��A�_���ψ�����������B
|
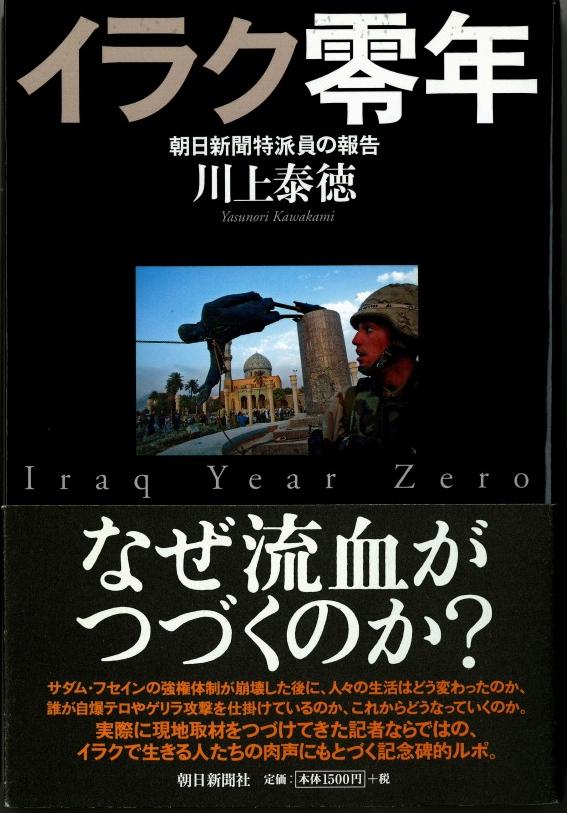
|
2009�N10�����A�v�l�Ɠ�l�ŃG�W�v�g�E�A���N�T���h���A�ɒ��݁i�Љ�l�̒����A��w���̒��j�͓��{�ɗ��܂����j�B�������݂̕ҏW�ψ����_���ψ��Ƃ��āA�C���N�A�C�X���G���A�p���X�`�i�ȂǕ����̐₦�Ȃ������̃��|�[�g�𑱂��Ă���B
2009�N�t�A�����V�����J�n�����L���C���^�[�l�b�g�}�K�W���ŁA�wAsahi�����}�K�W���x�𗧂��グ�A�ҏW�l�Ƃ��āA�j���[�X����A�R�������A�ڒ��B���G�œ����̌�������������A���̔w�i���Ђ��Ƃ��Ȃ��������Ă���B
�����n�т���ɍs���āA�������ɂ��S�z�������Ă��܂��B
�܂��A�g���x�������ċA���Ă��܂��h�Ƃ��������ł���(��)�B
- �����ɂ́A���炭�؍݂Ȃ��邻���ł��ˁB

|
| �T�}���ɂ�(2006�N�j |
�u2006�N�ɋA�����ĕҏW�ψ��ɂȂ�����ł����A����ȍ~���N��5�炢�͒����Ɏ�ނŏo�����Ă�����ł��B�������A���{���璆���͉����āA���{�ɂ����璆�����L�҂ƌ����Ă������̂��Ƃ͂悭������Ȃ��B
60�̒�N�܂œ��{�ɂ���̂͂��₾�Ǝv���āA�u�����ɒ��݂���������Ђ̌o��������v�Ƃ������R�Ŋ�]���o������A�F�߂�ꂽ�Ƃ������Ƃł��ˁB�ҏW�ψ��̔C����3�N�ōX�V������ł����A2009�N4���ɍX�V���ꂽ�̂ŁA���̍X�V��2012�N��4���B���Ȃ��Ƃ�����܂ł́A�����Ŏ�ނ𑱂������Ǝv���Ă��܂��v
- �k���̓������̕����A�s�s����J���ꂽ�Ƃ��B
�u�{���ɂ��肪���������ł��ˁB���������C���N���̃p���X�`�i���̕����n�����Ɏ�ނɍs���Ă��邩��A�������ɂ��S�z�����Ă����ł��B�܂��A"���x�������ċA���Ă��܂�"�A�Ƃ����������Ȃ��i�j�B���Ƃ��ẮA "����"���y����ł��܂��Ƃ��������ł����v
- ��コ�k���ɓ��w�����̂�1971�N4���ɂȂ�܂��ˁB
�u������|�X�g�c��̐���B���㗴�����4���ɂȂ�̂ŁA�w�������ōr�ꂽ�k����m��Ȃ����߂Ă̊w�N�Ȃ�ł��B2�N��3�N�́A�����ڌ��Ă���킯�ł�����ˁB
�ł��A�Ȃ����R�ȕ��͋C�͎c���ĂāA���������R�ł������A�w�Z�̊O�ł͎������F�߂��Ă��܂����B�������������ŁA�����ɂ��Ă������ɂ��Ă��A���k�̏W��Ō��܂��Ă����Ǝv���܂��ˁv
- �U��Ԃ��āA�ǂ�Ȗk�����ł������H
�u���`��c�c�A�_���Ɩ{�����������ł��ˁB�_�����ł̓L���v�e�����Ƃ߂Ă�����ł����A�_���̕����ȊO�́A�Ђ�����{��ǂ�ł܂����ˁB�����ƂɂȂ肽���Ǝv���Ă�����ł���B
���Z2�N�����牺�h�ɂȂ��āA�w�Z�̕��͂��Ȃ��Ȃ�܂����B���ԂƂ������̂Ƃ�����e�X�g���͂قƂ�ǂ������Ƃ��Ȃ��i�j�B�ł����͎�����͋[�����ł���Ȃ�̌��ʂ��������߂́A�܂�̂��߂̕������͂��Ƃ������߂��w���ł����ˁi�j�B���͂ɗ������̂�����ŁA�˂������Ă�A�ς��҂ł����B���������Ƃ�����������́A"��[�����ł����˂�"�Ə��܂������ˁv
- �_�����ł������������肵����ł����H
�u�����A�����A�����͒���������(��)�B��3�̍��̘A�̎��̓L���v�e���Ƃ����ӔC�������ăX�|�[�c����ɂ��āA���ꂪ���̂܂ܑ��ƃA���o���̎ʐ^�ɂȂ��Ă܂����B
���ƁA���̂��돸�i�����ɍs���ƁA��ŏ_�����K���Ă�ĕ��������肵����ł���B���i�̎����œ��������̂��A�������N��̕ĕ��B�̊i���̗͂��������肷���āA�����ɉ��������܂�ĕ������̂��o���Ă܂�(��)�v
- �ĕ����_���̏��i�����ɎQ������Ȃ�āA�����ۂ炵���ł��ˁB�k���̐搶�̎v���o�́H
�u�悭�A"�k���̐��k�́A����Ƃ��͒����4����萬�т��������ǁA�o��Ƃ��͔�����Ă���"�ƁA�搶�����������Ă����̂��o���Ă��܂��i�j�B���Ƃ����āA���т�����d������킯����Ȃ���������B���k�̎��含�d����搶�����������ł��ˁB
�S�C�́A1�N���̎��͉p��̊O���搶�A2�N�͍���̔�n�搶�A3�N�͉p��̌É�搶�ł����B�É�搶�Ƃ͂��܂��A������Ă܂��ˁB��n�搶�́A�l���{����ǂ�ł���̂�m���Ă��āA"���܂����͓ǂ̂�"�ƕ����ꂽ�̂�"�͂��S���ǂ݂܂���"���ē�������A"���Ⴀ����A�ǂ�ł݂�"���ēn���ꂽ�̂��A���|�]�_�ƁE�]���~�̑�\��w���Ƃ��̎���x�B�����A�V���I�������1���Ƒ�2�����o�Ă�����ł����ǁA�����݂��Ă��ꂽ��ł��v
- ���o�g�̒��w�́H
�u�������ł��B���e�����̌������������̂ŁA����8�N�Ԃ͑Δn�ŁA��3�Ŏ����ɗ�����ł��B�ŁA�l���k���ɓ����Ď������獲�X�Ɉ����z�����̂�1�N�ڂ͒ʂ��Ă���ł����A2�N����͉��h�B�������̘d���t���ł��ˁB�_�����̌m�Â��ċA�����炿����ƐQ�āA�ڂ��o�߂�������邩�A������ǂނ��A�������Ƃ��������B�Z�҂Ƃ������ꂽ��A�����������Ă܂����B
�@�m������̕��W�������āA1�N����3�N�܂ł̉ċx�݂̍앶����e�N���X�̗D�G�삪1�҂Ƃ������ł����A���e�p��3�`4���܂łƂ����K�肪������ǁA�l�͖��N10�����炢�̒Z�ҏ����������Ă܂����i�j�B3�N���̎��́A�w�����Ɠ������́x�Ƃ����^�C�g����15�����炢�Z�ҏ�������������ł����A���R�A�����čڂ����Ȃ��B����Ƃ��Ė��O�����͍ڂ��Ă܂������ǂˁi�j�B����������̕��w�I�˂�����ŁA�s�v�c�Ȃ��炢���ʂɂ��Ă���̂����₾�����v
- �������ɂ́A�����ۂ�ɂ��������w�i����2����1�x�̍�ҁE�������ߎ��������������ł��ˁB
�u�����Ƃ́A���Z���ジ���ƒ����悭�āA3�N���̎��������N���X�������̂��ȁB�悭���܂�ɂ������肵�܂����ˁB
�l�́A�����w�u�����������ǁA�ނ̓G���^�[�e�C�����g�ɋ߂������������D���ł����B���̍�i�ɒʂ�����́B�ނ͊ےJ�ˈꂪ�D���������Ǝv���B
�@���w�_���킹���Ƃ������Ƃ͂Ȃ���ł����A�������K���׃^�C�v����Ȃ��������玗�����̓��m�����������i�j�B�ł��A�����̖k���͂��������݂�Ȃ���Ȋ����ł����B�X�|�[�c������Ă���A���y������Ă���A��ɐ����Ă�����A�i�w�Z�Ȃ̂ɁA�����̓����Ă��܂��A�݂����Ȃ�����肪����܂����B���v���o���Ă��A���ɂ͌��I�Ȑ��k�����������Ǝv���B
�@�����Ƃ́A���Z���Ƃ��Ă�����A������肠���Ă��āw�i����2����1�x���A�u���镶�w�܁v����܂����Ƃ��́A"�܂����炤���ƂɂȂ������ǁA�薼���������Č�����"�Ƒ��k��d�b�Ŏ����Ƃ��������B
���̂��뎄�͐V���L�҂ɂȂ��Ă��āA���m�ŋ삯�o���L�҂����Ă��܂����B�ނ̌��̑�͊m���w���͖�Aⴂɏ���Ĕ�ԁx�������Ǝv���܂��B�l�́w�I���̎n�܂�̏I���x�݂����ȁA�������������������ǁA�l�̃A�C�f�A�͍̗p����܂���ł�����(��)�B
����30�N�߂��̂����ǁA����ȍׂ������Ƃ��o���Ă��܂��v
- ��コ���D����������Ƃ́H
�u�d�h��������ł���B���{�̌ÓT�A���Ƃ��A�Ėڟ��Ⓡ�蓡���͍�2�̂Ƃ��ɂ͑S���ǂ�ł��āA���Ƃ́A��]���O�Y�∢�����[�A�Ŗ��َO�Ƃ��B���Z����ɂ͏��i�O�́w�ԓ��Ђ����C�����āx�A�O�c���O�́w�l���ĂȂɁH�x�Ƃ����b��ɂȂ��ēǂ݂܂����ˁB���ꂩ��t�����X���w�ŁA�J�~����}�����[�B�l���A���Z���ł����Ƃ��e�������̂̓J�~���ŁA�l�́A��w�ł̓t�����X���w����肽���Ȃ��Ƃ͎v���Ă�����ł��v
- ��w�́A���O���w�̃A���r�A��w�ȁB�t�����X���w����]�����ꂽ��ł����H
�u�Ƃ��낪�A��������Ȃ���ł��B�A���r�A��́A���̓J�~���łȂ����Ă����ł��ˁB�J�~���́A�A���W�F���A���܂�̃t�����X�l�ŁA��\��ł���w�ٖM�l�x�ɂ��Ă��w�y�X�g�x�ɂ��Ă��A���W�F���A������B���́A�A���W�F���A�̓A���r�A��Ȃ�ł��B�t�����X���w�ƃA���u�Ƃ����̂́A�J�~����ʂ��āA�\�Ɨ��̊W�ɂ����āA�������A�t�����X�̐A���n�������A���W�F���A�́A�A���҂̎q���Ƃ��Đ��܂ꂽ�J�~���̂Ȃ��ł͉A�̕����B�J�~���̍�i�̒��ŃA���W�F���A�Ƃ�������̕s�C���Ȋ����Ɏ䂩��Ă�����ł��B
�����A������w�͈���Z�A����Z����ŁA����Z�͈�Q���ē���̕��w�������ł����A�ꎟ�ŗ����܂��Ăˁi�j�B2�Ԗڂ̑I��������������c�̈ꕶ�ɂ͎������ǁA���u�]�ɊȒP�Ɉꎟ�ɗ��������������ŋt�o�l�������āA�ŏ��́A�J�~���Ȃ���ŁA�܂��߂ɍs���Ƃ͍l���Ȃ��œ���Z�̑��O��A���r�A��Ȃ��o�肵�Ă����̂ł��B�������A�͂��݂ŃA���r�A�����邱�ƂɂȂ�����ł��B���w�u�]����������A����c���w���ɍs���悩�������ǁA�Ȃ����u�]�ɗ����āA���u�]�ɍs���Ƃ����̂��A�����Ƃ��Ă������肱�Ȃ��āA�����őI��ŃA���r�A��Ȃɍs�����Ǝv���܂����B
�V���Ђɓ����Ă�����A�Ȃ��A�A���r�A���������̂��A�ƌ�����̂ł����A�����������Ƃ������A��C�̎���ł��ˁB�ł��A���������̂������Ő����Ă������Ƃ����A����ȕς�����Ƃ�����k���Őg�ɕt������ł��傤�i�j�v
- �ǂ�ȑ�w���ł������H
�u��w�̂Ƃ����{������ǂ�ł�����ł����A�O�����Ă����Ȍ�w������Ă�l�Ԃ��W�܂��Ă邩�琢�E��m�邱�Ƃ��ł���B�����v���āA�w���㐢�E�����T�[�N���x�Ƃ����T�[�N��������ł��ˁB�ł�����́A�����Ԃ�āA���ɑ�w�̐V���ǂ��o���Ă���w���O��V���x�Ƃ����^�u���C�h���̐V���̕ҏW��������āA�W���[�i���Y���ɋ��������B�ł��{�Ƃ̃A���r�A��͖{���ɓ���āA�����Ȃ��ƃ_���Ȃ�ł���B������4�N���̂Ƃ��ɁA�G�W�v�g�̃J�C����w��1�N�ԗ��w���āA���̎��͈ꐶ��������������A����ƃA���r�A�ꂪ�g����悤�ɂȂ�܂����B���w���I���ċA�����āA���_�������Ȃ���A�����V���������ł��v
- ���Ђ�1981�N�Ƃ̂��Ƃł����B
 �u�����ł��B�������A�A���r�A�������Ă���̂ɁA�V���Ђł͒n���x�ǂ�5�N�ԁA�����{�Ђł͊w�|����6�N�Ԃ��āA�����Ƃ͂����ƊW�Ȃ��L�Ґ����ł����B
�u�����ł��B�������A�A���r�A�������Ă���̂ɁA�V���Ђł͒n���x�ǂ�5�N�ԁA�����{�Ђł͊w�|����6�N�Ԃ��āA�����Ƃ͂����ƊW�Ȃ��L�Ґ����ł����B
����10�N�ڂ��炢�ɁA�����̕ǂ̕���ł��B�����A���E�ς����炪��ς���Ă���������ł���ˁB�C�f�I���M�[�̊�Ղ�����čs���킯�ł����A������������̏ے��������̂��A�����ł��B���h���Ƃ��ăJ�C���ɕ��C�����͓̂���12�N�ڂ�1993�N�ł��B2001�N��9��11���A�u9�E11���������e�������v���G���T�����Ō}�����ł����A���́u9�E11�v�����E��ς����o�����ł����ˁB
�@�����A�������댯�n��ł��邱�Ƃ͊m���Ȃ�ł���B�C���N�푈�̎�ނ̂Ƃ��́A��ɂȂ����烍�P�b�g�e�����ł邵�A���A�z�e���Ƀ~�T�C�����ł����܂�Ėڂ��o�߂����Ƃ�����B��ɋْ�����������ł����B�悭���_�I�ɂԂ�Ȃ������Ȃ��Ǝv����ł����A��Ɏ����Ƃ��Ă̖��ӎ��������āA�������̒��ł����������ł��Ȃ���ނ����āA���������������Ƃ��ł��Ȃ��L�����������Ƃ��܂����B
�C���N�̃W�v�V�[�̂��ƂׂĂ݂悤�Ƃ��A�C���N�푈�̌�ɏo������U�̃p�X�|�[�g��N�������Ă��邩����ނ��Ă݂悤�Ƃ��A�Ƃɂ����A�������C���N�ɂ������A���������炵���L�������������Ǝv���킯�ł��B
�������č��Z�����U��Ԃ��Ă݂�ƁA�k���̍Z���Ƃ���"��Ɏ����ōl���邱��"��g�ɂ��Ă������炩������܂���B���������炵���ɑ��邱����肪�����āA���̂��ƂɎ��o�I����������A�������ł��g�ɂȂ炸�ɁA�^�t�ł���ꂽ��Ȃ����Ǝv���܂��v
- �Ȃ�قǁB�Ō�ɁA���������Z��������Ă�����������y�����ɂЂƂ��ƁB
�u���R�ȍZ��������Ă�����������y���ɂ́A���ӂ��������B���肪�����ł���B���̎��R�����������炱���A�݂�Ȃ������炵���l���A�����Ȃ��Ⴂ���Ȃ��Ƃ������͋C�ɂȂ��Ă����Ǝv���B���̕��A�ςɂ��ς��Ă�����A���낢��Y�肵�܂����B
�搶�����͐��k�����ɂ��ƂȂ��������Ăق������낤����ǂ��A�������肵�Ă�������A���Z����Ɏ����炵�������邱�Ƃ�T��ق����A�Љ�ɏo�Đ��������ɂ͑�Ȃ��Ƃ��Ǝv����ł���B�Љ�͌���������A�����^����ꂽ�d�����������������A�����炵���d�������邽�߂̂ق����A�����Ɨ͂��o��Ǝv���܂��B
���̂��l���Ȃ���Ȃ�Ȃ����Z����A����ȍZ���̂Ȃ��ʼn߂������Ƃ��ł����̂́A�{���ɂ悩�����Ǝv���B�k���̍��Y���Ǝv���܂��B�厖�ɂ��Ă䂫�����ł��ˁv
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@
|



